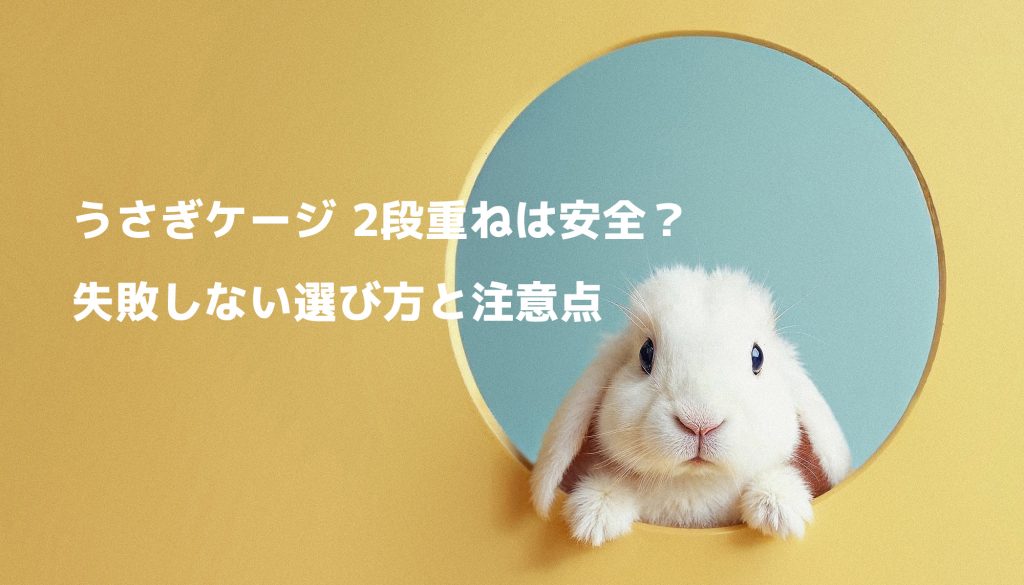
うさぎを多頭飼いしている、あるいはこれから飼いたいと考えている方にとって、「うさぎ ケージ 2段 重ね」というスタイルは省スペースで便利に思えるかもしれません。とはいえ、実際に導入するとなると安全性や快適性、掃除のしやすさなど、気になるポイントがいくつも出てきます。本記事では、うさぎに2段ケージってどうなの?安全性と快適性を解説しながら、こんな人に2段ケージはおすすめ!あなたは当てはまる?という視点でもご紹介していきます。
さらに、うさぎの多頭飼い、ケージ選びで絶対に失敗しないために押さえておきたいポイントや、2段ケージのメリットとデメリット【リアルな口コミ付き】もあわせて解説。2段ケージを選ぶときのチェックポイント5つや、2段ケージで起こりがちなトラブルとその対処法など、実用的な情報を網羅しています。
また、「おすすめの2段ケージはこちらです!」という具体的な商品提案や、2段ケージはDIYできる?自作する場合の注意点とコスト感についても触れ、2段ケージ+αで快適に!合わせて買いたい便利グッズ5選まで、幅広くカバーしています。これから2段ケージを検討している方にとって、実践的かつ安全性を重視した参考になる情報をお届けします。
この記事でわかること
- うさぎに2段ケージを使う際の安全性と注意点
- 上下移動がない独立型2段ケージの重要性
- 多頭飼いにおけるケージ選びの基本と工夫
- おすすめの2段ケージや便利グッズの情報
うさぎ ケージ 2段 重ねは安全に使える?
- おすすめの2段ケージはこちらです!
- うさぎに2段ケージってどうなの?安全性と快適性を解説
- 2段ケージのメリットとデメリット【リアルな口コミ付き】
- 2段ケージを選ぶときのチェックポイント5つ
- 2段ケージで起こりがちなトラブルとその対処法
- 2段ケージはDIYできる?自作する場合の注意点とコスト感
おすすめの2段ケージはこちらです!
快適・清潔・安心設計!小動物のための万能ケージ
【便利な移動&お手入れラクラク】
ハンドル付きで持ち運びが簡単。底部の取り外し可能なトレーは掃除がしやすく、排泄物やゴミをスムーズに処理できます。旅行や外出先でも使いやすい設計です。
【多用途で見やすいデザイン】
ハリネズミ、モルモット、モモンガ、ウサギなど、小動物全般に対応。どの角度からも中の様子が確認しやすく、ペットの様子をしっかり見守れます。
【丈夫で安心な素材】
天然モミ材を使用し、防水加工済み。外での使用にも適しており、ペットが安心して過ごせる通気性の良い作りです。外敵の侵入も防ぎます。
【簡単組立&自由な出入り】
組み立てが簡単で一人でも設置可能。開閉可能なドアで、小動物が自由に出入りでき、運動不足の解消にも役立ちます。

小動物うさぎ ケージ2層うさぎ ケージ 室内 簡単持ち運び便利 春夏 小屋 ワイヤーケージ キャットうさぎ 家組み立て 簡単,ワイド扉 多頭飼い 脱走防止ウサギ 飼育ゲージうさぎゲージ大きいうさぎ用 柵
2段ケージを選ぶ際に重要なのは、安全性・掃除のしやすさ・うさぎへの配慮の3点です。単にスペースを縦に使えるから便利という理由だけで選ぶのではなく、うさぎの体格や生活スタイルを考慮して選ぶ必要があります。
安全性を重視する場合は、アクリル素材のクリアケージも選択肢に入ります。アクリルはうさぎの噛み癖に強く、透明なため外から様子が確認しやすいのが特徴です。これにより、体調変化に早く気づけるというメリットもあります。
ただし、これらの製品を使用する場合でも、上下のケージが独立している構造であることが前提です。つまり、うさぎが自分で上段と下段を行き来する「内部2階建て構造」ではなく、上下で完全に分かれた設計になっていることが重要なのです。
また、DIYでケージを設置する人の中には、スチールラックを活用してケージを上下に配置する方法を取る人もいます。これは製品自体を積み重ねるよりも安定感があり、安全に管理できるという点で注目されています。
2段ケージを選ぶ際は、製品のサイズ、うさぎの種類、設置スペース、掃除の頻度などを具体的に想定しながら選ぶことが大切です。価格や見た目だけでなく、日々の管理と安全性のバランスを重視して検討しましょう。
うさぎに2段ケージってどうなの?安全性と快適性を解説
うさぎにとっての2段ケージは、必ずしも快適な環境とは言えません。上下を行き来できる構造の2階建てケージは、見た目には省スペースで効率的に見えても、実際にはうさぎに大きな負担を与える危険性があります。
うさぎは非常に繊細な骨格を持つ動物で、骨が中空構造になっており骨折しやすい性質があります。そのため、上下に飛び移るような行動が求められるケージは、大きな怪我のリスクを伴います。特にロフトやスロープが付いたタイプでも、すべてのうさぎが安全に使えるわけではなく、途中で落下してしまう事故も報告されています。
このような背景から、獣医師やうさぎ専門店では「内部2階建てケージ」は推奨されていません。むしろ、広めの1段ケージを使い、ケージ外での運動時間を確保することがうさぎにとって快適な飼育環境となります。
一方で、「上下が完全に独立した2段ケージ」であれば、多頭飼い時にスペースを有効活用するための選択肢となります。この場合、うさぎが上下を移動することはなく、それぞれのケージが独立して安全な環境を保つことができます。
快適性の面でも、ケージの広さや天井の高さ、通気性などが大きな影響を与えます。例えば、立ち上がっても耳が天井に触れない設計や、掃除しやすい構造であれば、うさぎも安心して生活できるでしょう。
まとめると、上下を自由に移動させる構造は避け、独立型2段ケージか、広い1段ケージ+運動スペースの確保が、うさぎにとって安全かつ快適な飼育スタイルになります。
2段ケージのメリットとデメリット【口コミ】
2段ケージには、省スペースで多頭飼いが可能になるという大きなメリットがあります。しかしその一方で、使用にあたっては注意すべきデメリットも存在します。
まずメリットとして挙げられるのは、ケージを縦に重ねることで限られたスペースを有効活用できる点です。部屋に横幅の余裕がない場合でも、縦に設置することで複数のうさぎを飼うことができます。また、上下でうさぎを分けることで、それぞれのテリトリーをしっかり守ることができ、ケンカの予防にもつながります。
一方、実際の口コミには、「2段ケージにしたら先住うさぎの食欲が減った」「上段の掃除が面倒で手が届きにくい」といったマイナスの声もあります。特に音や気配で上下のうさぎ同士が存在を意識してしまい、ストレスを感じる個体も少なくないという指摘が見られます。

2段ケージにしたら先住うさぎの食欲が減った
上段の掃除が面倒で手が届きにくい

例えば、うさぎが足ダン(床を蹴って音を立てる行動)を頻繁にするようになり、音や振動が下のケージに響いてしまうことで、下のうさぎにストレスを与えるケースもあります。さらに、ケージの安定性が不十分である場合は、地震や衝撃で倒れるリスクもあるため、安全対策は必須です。
このように、2段ケージの導入には確かに利点がありますが、それは設置の工夫やうさぎの性格への配慮があって初めて活かせるものです。リアルな体験談からも、見た目やスペース効率だけで判断するのではなく、飼育環境全体のバランスを考えた判断が求められるといえるでしょう。
2段ケージを選ぶときのチェックポイント5つ
ポイント
- サイズの適合性
立ち上がっても天井に届かず、寝そべっても壁に触れない広さ(横幅50cm以上、奥行50〜60cm、高さ40cm以上)が理想。 - 安全性の確保
倒れにくい安定構造で、耐荷重が明記されたものを選ぶ。上下段がつながっていない独立型が安心。 - 掃除・お世話のしやすさ
上段にも手が届くように、フルオープンタイプや引き出しトレイ付きのケージが便利。 - 素材と床の工夫
足を挟まない細かめのメッシュや樹脂製床が安全。柵は噛み癖を考慮して丈夫な素材(スチール・アクリルなど)を選ぶ。 - 設置場所との相性
通気性がよく、静かで直射日光の当たらない場所に設置。防音マットやキャスター付きで移動・掃除もラクに。
うさぎ用の2段ケージを選ぶ際には、安全性と快適性の両方を満たすために、いくつかの重要なポイントを押さえておく必要があります。ここでは、実際に使用する前に確認しておきたい5つのチェックポイントを紹介します。
1つ目は「うさぎの体格に合ったサイズ」です。立ち上がっても頭が天井にぶつからない高さ、そして寝そべったときに体が壁に触れない広さが必要です。小型のうさぎでも、横幅は50cm以上、奥行きは50〜60cmが理想とされており、高さも40cm以上あると安心です。ケージのサイズが合っていないと、ストレスや運動不足の原因になります。
2つ目のポイントは「安全性」です。2段ケージは構造上、高さが出るため、地震や物音などで倒れてしまうリスクがあります。しっかりと固定できる構造であること、また、ケージ自体の耐荷重が明示されている製品を選びましょう。上下のケージがつながっていてうさぎが自力で行き来できる構造は避け、あくまで独立した段として設置するのが安全です。
3つ目は「掃除やお世話のしやすさ」です。特に上段のケージは手が届きにくく、日常的な掃除やうさぎの出し入れが面倒になりがちです。そのため、天井や前面がフルオープンできるタイプや、引き出しトレイ付きの製品を選ぶことで、手入れの負担を軽減できます。
4つ目は「床材やケージの素材」です。床はすのこやメッシュが使われることが多いですが、穴が大きすぎると足を挟んでしまうことがあるため注意が必要です。細かめのメッシュや、樹脂製の床など、足に優しく安全なものを選びましょう。また、柵の素材はスチール製やアクリル製が多く、うさぎの噛み癖を考慮して選ぶことが大切です。
5つ目は「設置場所との相性」です。ケージは通気性が良く、直射日光が当たらない静かな場所に置くことが基本です。集合住宅などでは騒音や振動にも配慮し、防音マットなどを敷くのも一つの工夫です。キャスター付きのケージであれば、掃除やレイアウト変更もしやすくなります。
これらの5つのポイントを丁寧にチェックしておくことで、2段ケージでも安全かつ快適にうさぎを飼うことができます。
2段ケージで起こりがちなトラブルとその対処法
2段ケージは便利な反面、実際に使用してみるといくつかのトラブルに直面することがあります。トラブルの多くは事前に対策することで回避できますが、予想外の問題もあるため、飼い主としては柔軟な対応力が求められます。
まず最も多いのが「うさぎの落下によるケガ」です。上下を行き来できる構造になっているケージでは、ジャンプやスロープの使用中に滑ってしまい、骨折してしまうケースが少なくありません。うさぎの骨は非常にもろいため、少しの衝撃でも大きな怪我につながることがあります。これを防ぐには、うさぎが上下移動できないように、上下のケージを完全に独立させて設置することが前提となります。
次に「うさぎ同士の気配によるストレス」があります。上下にうさぎを配置すると、直接の接触がなくても気配やにおい、物音から他のうさぎの存在を感じ取ります。特に縄張り意識の強いうさぎにとっては、こうした間接的な刺激でもストレスの原因になることがあります。このような場合は、視覚的に区切るための布や仕切りを使ったり、ケージの位置を調整したりすることで対応できます。
さらに、「掃除がしにくい」という意見も少なくありません。上段のケージに手が届きにくく、結果的に掃除の頻度が落ちてしまうケースがあります。これを防ぐためには、キャスター付きの台や踏み台を活用するほか、天井が大きく開くタイプのケージを選ぶことが有効です。
他にも「騒音や振動によるトラブル」も報告されています。うさぎが足ダンをしたとき、その音が床を通じて下段のケージに響いたり、隣の部屋に伝わったりすることがあります。特に集合住宅では注意が必要です。対策としては、防音マットやジョイントマットをケージの下に敷くことで、振動を軽減することができます。
これらのトラブルは、使用前に正しい知識を持ち、必要な準備を行うことで多くが回避可能です。うさぎの様子をよく観察し、少しでも異変があれば速やかに環境を見直す姿勢が大切です。
2段ケージはDIYできる?自作する場合の注意点とコスト感
2段ケージは市販品だけでなく、DIYによって自作することも可能です。特にスペースに合わせたオリジナル設計をしたい場合や、コストを抑えたいと考えている人にとっては、DIYという選択肢は魅力的に映るかもしれません。
まず結論から言えば、DIYで2段ケージを作ることは十分可能です。ワイヤーネット、結束バンド、スチールラック、木材など、ホームセンターや100円ショップで手に入る素材で構成できるため、材料の入手も難しくありません。実際、費用を抑えた例では、1段あたり1,500円程度、2段で約3,000円〜5,000円ほどで作成しているケースもあります。
しかし、自作において最も重要なのは「安全性の確保」です。ワイヤーの接合部が緩かったり、全体の強度が足りないと、うさぎの動きによって崩れる危険性があります。結束バンドだけで固定していると、重さや振動でズレが生じることもあるため、金具やネジによる補強が必要になる場合があります。
また、DIYでよく見かけるのが「うさぎが上下を自由に移動できる2階建て構造」です。これは見た目は魅力的かもしれませんが、前述の通り、骨折などの重大な事故につながるため避けましょう。DIYであっても、上下が完全に分かれた独立型の2段構造にすることが基本です。
さらに注意したいのが「素材の選定」です。うさぎは何でもかじる習性があるため、塗料が塗られた木材や、有害なプラスチックを使ってしまうと健康被害の恐れがあります。無垢材や食品用グレードの樹脂など、安全性の高い素材を選ぶようにしてください。
掃除のしやすさや、メンテナンス性にも目を向ける必要があります。トレイの取り外しができるように設計したり、扉が大きく開く構造にすることで、日々の手入れがずっと楽になります。
このように、DIYはコスト面で有利ですが、手間と設計力、安全管理への責任が伴います。自作する場合は、うさぎの特性をよく理解し、完成後も定期的な点検や補強を忘れないことが大切です。
うさぎ ケージ 2段 重ねの選び方とおすすめ
- こんな人に2段ケージはおすすめ!あなたは当てはまる?
- うさぎの多頭飼い、ケージ選びで絶対に失敗しないために
- 2段ケージ+αで快適に!合わせて買いたい便利グッズ5選
- 設置場所と通気性にも注意しよう
- まとめ:うさぎの安全を守るケージ選びとは
こんな人に2段ケージはおすすめ!あなたは当てはまる?
2段ケージは誰にでも向いているわけではありません。しかし、うまく活用すれば、うさぎにとっても飼い主にとっても便利な選択肢になります。ここでは、2段ケージが特におすすめな人の特徴を紹介します。
まず、多頭飼いをしている人には2段ケージがとても有効です。うさぎは縄張り意識が強く、同じケージで複数を飼うとケンカやストレスの原因になります。一羽ずつ別のケージで飼うことが基本となりますが、横に並べるスペースが確保できない場合、上下に重ねることで省スペース化が可能です。ただし、上下のケージはしっかりと分離された構造であることが前提です。
また、住居スペースが限られている人にも適しています。ワンルームやマンションでうさぎを飼っている場合、ケージを横に並べると生活スペースが圧迫されます。そのようなとき、縦の空間を活かした2段ケージは設置しやすく、部屋全体をすっきり保つことができます。
掃除や世話の効率を重視する人にも2段ケージは便利です。例えば、キャスター付きで移動しやすいタイプや、上下それぞれに引き出しトレイがあるケージを選べば、掃除も楽に行えます。掃除する際に、汚れた段だけを取り出して対応できる構造であれば、手間を軽減できます。
一方で、うさぎが上下を自由に行き来する2階建て構造を希望する人には不向きです。ジャンプや移動によって骨折のリスクが高まるため、安全面からおすすめできません。同様に、ケージの設置が不安定になりやすい環境(地震の多い地域、床が柔らかい場所)でも、2段ケージの導入は慎重に検討すべきです。
このように、多頭飼いでスペースを有効に使いたい人、部屋が狭い人、効率よく世話をしたい人には2段ケージが非常に向いています。反対に、安全面や構造的な配慮を十分に取れない場合は、導入を控えるほうが賢明です。
うさぎの多頭飼い、ケージ選びで絶対に失敗しないために
うさぎの多頭飼いは、にぎやかで楽しい反面、トラブルが起こりやすく注意が必要です。特にケージの選び方を誤ると、ストレスやケンカ、健康被害など、深刻な問題につながることもあります。そこで、失敗しないケージ選びの基本ポイントを押さえておきましょう。
まず最初に理解しておきたいのは、「うさぎは基本的に単独飼育が向いている動物である」ということです。縄張り意識が非常に強く、同じ空間で他のうさぎと過ごすことが大きなストレスになる場合があります。そのため、多頭飼いをする場合でも、1羽につき1ケージを用意するのが鉄則です。
次に大切なのが、ケージの配置と距離感です。複数のケージを置く場合、うさぎ同士の距離が近すぎると、見える・聞こえる・においがするというだけで威嚇行動を取ることもあります。必要に応じて、仕切りやカバーで視界を遮る工夫も検討しましょう。
また、それぞれのケージに個別の飼育用品を用意することも忘れてはいけません。トイレ、エサ入れ、水入れ、隠れ家、おもちゃなどは共用せず、各うさぎ専用にするのが基本です。これにより、トラブルやストレス、衛生上のリスクを最小限に抑えることができます。
うさぎ同士の相性と慣らし期間にも注意が必要です。最初から同じ部屋で放すのではなく、まずはケージ越しに対面させ、少しずつ慣れさせていく段階を踏むことが成功のポイントです。場合によっては、仲良くなることが難しい個体同士もいるため、そのときは無理に一緒に飼おうとせず、別の部屋で分ける判断も必要です。
最後に、多頭飼いは手間も費用もかかるという現実を理解しておくことが大切です。ケージや飼育用品、食事、医療費が倍以上になる可能性があるため、無理なく管理できるかどうかも含めて事前に計画を立てましょう。
このように、うさぎの多頭飼いを成功させるには、「個別の空間・個別の用品・相性の確認・ストレス管理」という4つの要素が欠かせません。どれも欠けてしまうとトラブルの原因になるため、慎重に準備を進めることが求められます。
2段ケージ+αで快適に!合わせて買いたい便利グッズ5選
2段ケージを導入するだけでは、うさぎにとって本当に快適な環境とは言えません。そこで、日常の世話をスムーズにし、うさぎの健康や安全を守るために合わせて用意しておくと便利なグッズを5つ紹介します。
1つ目は「トイレ用スノコ・トイレトレー」です。うさぎは意外とトイレの場所を覚える動物ですので、スノコ付きのトイレや引き出し式トレイを使えば、排泄物の処理がしやすくなります。特に2段ケージでは掃除が大変になりがちなので、汚れた部分だけを素早く取り外して掃除できる構造があると非常に便利です。
2つ目は「キャスター付きの台座やケージ台」です。2段ケージは高さが出るため、重くて移動しにくくなることがあります。キャスター付きの台座を使用すれば、ケージ全体を動かして掃除ができるだけでなく、安定性の向上にもつながります。
3つ目は「給水ボトルと専用ホルダー」です。特に上段のケージでは、水入れの転倒が心配ですので、しっかりと固定できるホルダー付きのボトルを設置することで、水がこぼれるリスクを減らすことができます。ボトルは透明で残量が確認しやすいタイプを選ぶと、日々の管理がより楽になります。
\👇給水ボトルの紹介はこちら👇/
4つ目は「滑り止め付きの床マットやジョイントマット」です。ケージの中は金属や樹脂製の床になっていることが多く、そのままでは足裏に負担がかかります。滑り止め効果があるマットを敷くことで、足のケガや滑りによる転倒を防げます。さらに、クッション性があるマットを選ぶと、足ダンの振動も軽減できます。
5つ目は「隠れ家やうさぎ用ハウス」です。うさぎは静かで暗い場所を好む傾向があり、外からの視線を遮る隠れ家があると安心感を得やすくなります。木製や布製など様々な素材がありますが、噛んでも安全なものを選ぶことが大切です。
これらのグッズを活用することで、2段ケージの利便性がさらに高まり、うさぎにとってもストレスの少ない、安心できる住環境を整えることができます。ケージ選びと同じくらい、こうした補助アイテムの存在も重要だと考えておきましょう。
設置場所と通気性にも注意しよう
うさぎ用の2段ケージを設置する際、サイズや構造だけでなく「置く場所」と「通気性」にも十分な配慮が必要です。うさぎはとても繊細な生き物で、環境のちょっとした変化がストレスや体調不良につながることがあります。
まず、設置場所についてですが、直射日光が当たる場所や、エアコンの風が直接当たる場所は避けてください。暑さや寒さに弱いうさぎにとって、急激な温度変化は体への負担が大きくなります。風通しがよく、年間を通して温度と湿度が安定しやすい場所が理想です。特に夏場は熱がこもりやすいため、日中に室温が上がる部屋では冷房の位置や温度設定にも注意しましょう。
次に気をつけたいのが通気性の確保です。密閉性の高いアクリル製のケージなどは見た目がすっきりしていて人気ですが、換気が不十分だとうさぎの健康に悪影響を及ぼす可能性があります。尿やフンのにおいがこもったり、湿気が溜まることで細菌が繁殖しやすくなるからです。このような状況を防ぐためには、ケージの周囲に適度な空間を空けて設置することが効果的です。壁に密着させすぎない、上下のケージに隙間を設ける、などの工夫をすることで空気の流れを作りやすくなります。
また、集合住宅に住んでいる場合には振動や騒音対策も重要です。うさぎが足ダンをしたときの音や振動が下の階に響かないよう、防音マットやジョイントマットを敷いておくと安心です。ケージ自体の揺れも抑えられるため、地震対策にもなります。
このように、2段ケージを設置する場所の環境を整えることは、うさぎの健康維持とストレス軽減に直結します。スペースが限られているからといって無理な場所に置いてしまうのではなく、温度、湿度、風通し、音、光のバランスが取れた空間を意識することが大切です。
まとめ:うさぎの安全を守るケージ選びとは
うさぎにとって快適な住環境を整えるうえで、ケージの選び方は非常に重要です。特に2段ケージのような特殊な構造を導入する場合は、利便性だけでなく、うさぎの習性や身体的な特徴を十分に理解したうえでの判断が求められます。
まず大前提として、うさぎは上下移動に適した動物ではないということを覚えておきましょう。骨がとてももろく、高さのある場所からのジャンプやスロープ移動で簡単に骨折してしまうリスクがあります。そのため、2段ケージを選ぶ際には「上下を行き来できる構造」を避け、完全に独立した2つのケージを縦に設置する方法を選ぶことが基本となります。
また、うさぎは縄張り意識が強いため、多頭飼いをする場合でも1羽ごとに独立したケージが必要です。2段ケージはこのようなシーンにおいて省スペース化の手段として非常に有効ですが、適切な距離感や視界の遮断などの配慮も忘れてはいけません。
さらに、日々の世話のしやすさや掃除のしやすさも重要なポイントです。特に上段のケージは手が届きにくくなるため、扉が大きく開く構造や、引き出しトレイ付きのケージを選ぶことで管理がスムーズになります。
もうひとつ見落とされがちなのが、設置場所の環境です。通気性が悪く、湿度がこもるような場所にケージを置くと、うさぎの体調にも悪影響を与えるおそれがあります。空気の流れがある場所に、安定した形で設置し、振動や騒音対策も行いましょう。
このように考えると、うさぎのケージ選びでは「スペース効率・安全性・管理のしやすさ・環境適応」の4つの軸が大切であるとわかります。どれかひとつを犠牲にすると、結果的にうさぎのストレスや健康問題につながりかねません。
あなたがうさぎのケージを選ぶときは、こうしたポイントを一つひとつ丁寧に確認し、見た目や価格だけに惑わされない選択を心がけましょう。それが、うさぎの命を守り、長く健やかな暮らしを支える第一歩となります。
うさぎケージ 2段重ねを安全に使うための総まとめ
- うさぎが上下を行き来する2階建て構造は避けるべき
- 上下で完全に分離されたケージ構造が安全
- 骨折リスクを防ぐためジャンプ移動をさせない
- 多頭飼いには独立型2段ケージが適している
- 設置スペースが狭い家庭では縦配置が有効
- ケージサイズは体格に合った広さを選ぶ
- 通気性と室温が安定する場所に設置する
- キャスター付きで移動しやすい製品が便利
- アクリル製やスチール製など素材にも配慮する
- 引き出しトレイ付きは掃除の手間を減らせる
- ケージの安定性と耐荷重を必ず確認する
- ストレスを防ぐため他のうさぎと視界を分ける
- 防音マットで騒音や振動への配慮が必要
- DIYの場合も安全性と素材選びに細心の注意を払う
- 快適性向上には隠れ家や滑り止めマットが有効
-

-
うさぎケージ 2段重ねは安全?失敗しない選び方と注意点
2025/7/15
うさぎを多頭飼いしている、あるいはこれから飼いたいと考えている方にとって、「うさぎ ケージ 2段 重ね」というスタイルは省スペースで便利に思えるかもしれません。とはいえ、実際に導入するとなると安全性や ...
-

-
うさぎ 給水 ボトルは良くない?後悔しない選び方と工夫を解説
2025/7/14
うさぎを飼っている方の中には、「うさぎ 給水 ボトル 良く ない」といったキーワードで情報を探している方も多いのではないでしょうか。うさぎの給水ボトルは「良くない」と言われる理由として、飲みにくさや水 ...
-
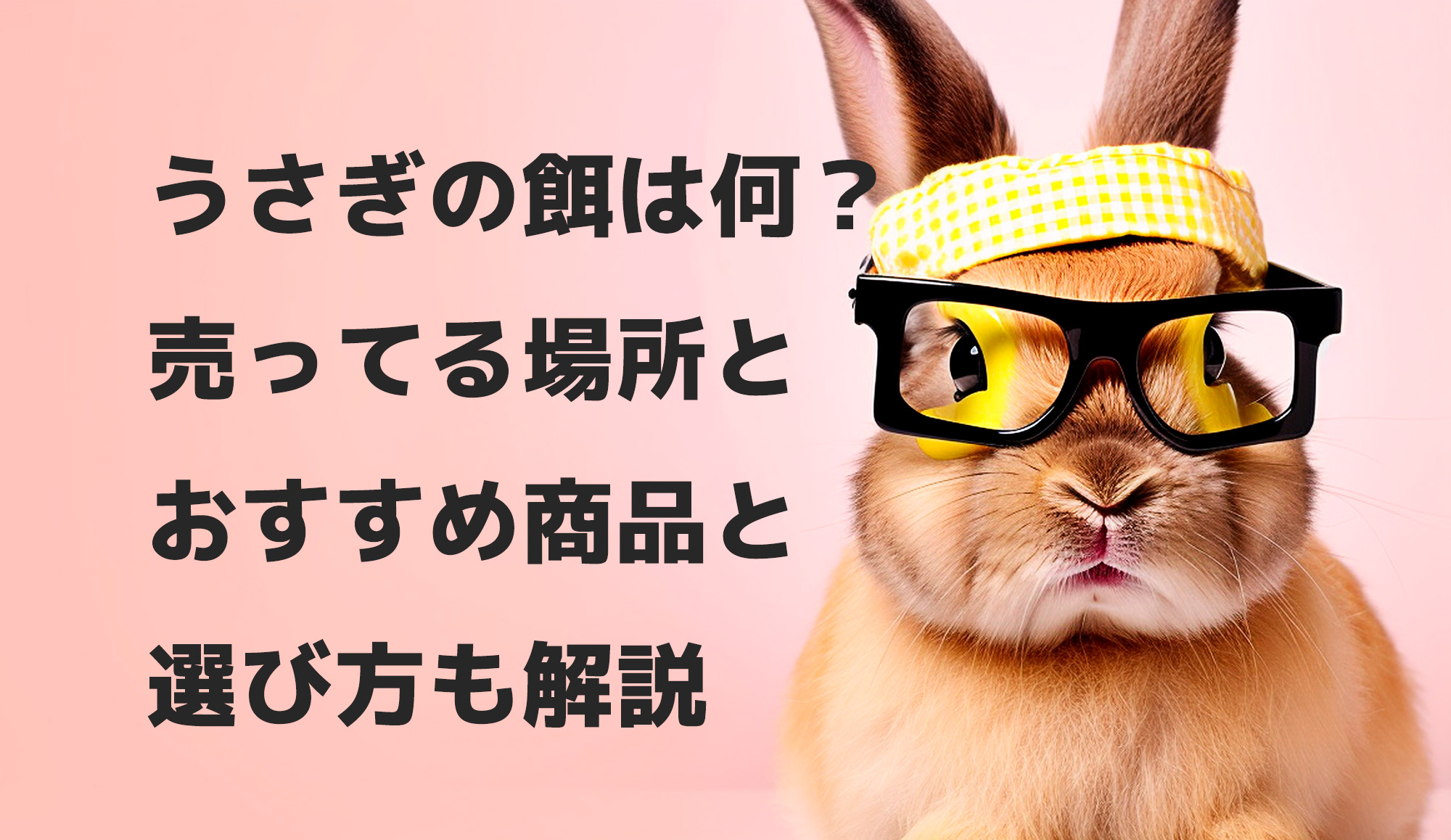
-
うさぎの餌は何? 売ってる場所とおすすめ商品と選び方も解説
2025/7/15
うさぎを飼い始めると、まず気になるのが「うさぎの餌の売ってる場所」ではないでしょうか。どこで餌を購入できるのかだけでなく、餌はなに?ペレットって?チモシーって?といった基本的な知識も押さえておくことが ...
-

-
【2025年版】うさぎ用自動給餌器(オートフィーダー) おすすめと選び方を詳しく説明します。
2025/7/15
この記事はプロモーションを含みます うさぎの健康を維持するためには、適切な時間と量での給餌が欠かせません。しかし、仕事や外出が多いと、毎回決まった時間に餌を与えるのが難しくなることもあります。そんなと ...
