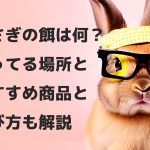この記事はプロモーションを含みます
うさぎの健康を維持するためには、適切な時間と量での給餌が欠かせません。しかし、仕事や外出が多いと、毎回決まった時間に餌を与えるのが難しくなることもあります。そんなときに役立つのが、自動給餌器(オートフィーダー)です。近年では、ペレットの給餌時間や量を細かく設定できるものだけでなく、カメラ付きのオートフィーダーも登場し、給餌時の様子を遠隔で確認できる便利なモデルも増えています。
とはいえ、どのくらいの容量が必要なのか、使うペレットの種類は限定されるのかなど、選ぶ際のポイントをしっかり押さえておくことが重要です。また、どのくらいのケージに取り付けられるのかや、ケージの種類によって取り付け方が変わるのかといった点も、購入前に確認すべきポイントです。さらに、停電でも機能するのかといった電源供給の仕組みも、安心して使用するためにはチェックしておきたい要素となります。
一方で、動作音がうさぎにストレスを与えることがあるため、音を減らす方法や、音を減らすための具体的な設定方法、さらには音を減らすためのアクセサリーなどを活用して、できるだけ静かに使えるように工夫することも大切です。実際に使用したユーザーの口コミも気になるところであり、「おすすめはありますか」や「口コミをもっと知りたい」といった疑問を持つ方も多いでしょう。
また、うさぎの主食である牧草に対応した給餌器はあるのかも気になるポイントです。牧草対応はありますかや、牧草を使用する際の注意点、牧草フィーダーの容量や価格帯など、牧草を与えるための最適な方法についても知っておくべきです。さらに、牧草フィーダーのおすすめや、牧草フィーダーで使える牧草の種類、牧草フィーダーで使えるフードの種類なども、うさぎの健康管理には欠かせません。
この記事では、うさぎ用の自動給餌器(オートフィーダー)のおすすめモデルや選び方、使用時の注意点などを詳しく解説していきます。うさぎの健康と快適な飼育環境を守るために、最適な給餌器を選ぶ参考にしてください。
この記事でわかること
- うさぎ用の自動給餌器の仕組みや選び方がわかる
- 各モデルの容量や機能の違いを理解できる
- うさぎに適したペレットや牧草フィーダーの選択基準がわかる
- 音や設置方法など使用時の注意点と対策を学べる
うさぎ 自動給餌器 オートフィーダー おすすめの選び方
- 自動給餌器オートフィーダーとは
- どのくらいの容量が必要?
- カメラ付きオートフィーダーの撮影範囲
- 停電時でも機能する?
- 使えるペレットの種類と注意点
- どのくらいのケージに取り付けられる?
- ケージの種類による取り付け方の違い
自動給餌器オートフィーダーとは

自動給餌器(オートフィーダー)は、設定した時間に自動でフードを供給できる便利な機器です。うさぎを飼っている方にとって、決まった時間に餌をあげることは健康管理の基本ですが、仕事や外出が多い場合、時間通りに給餌するのが難しくなることもあります。そのような場面で役立つのが、自動給餌器です。
一般的な自動給餌器は、ペレット専用のものが多く、あらかじめ設定した回数と量に応じて給餌されます。多くのモデルでは、1日2回から4回程度の給餌設定が可能で、1回あたりの給餌量も細かく調整できます。特に、うさぎは消化のために適度に食事を分けて摂る必要があるため、決まった時間に一定量のペレットを与えられるオートフィーダーは、健康維持に役立つアイテムです。
さらに、最近ではスマートフォンアプリと連携できるモデルも登場しており、外出先から遠隔操作で給餌のスケジュールを調整することができます。また、カメラ付きのオートフィーダーを選べば、給餌の様子やうさぎの状態をリアルタイムで確認することも可能です。
一方で、自動給餌器にはいくつかの注意点もあります。例えば、粘着性のあるフードや大きなペレットは詰まりやすく、機器が正常に作動しなくなる可能性があります。また、長期間の留守に対応するために大容量のタンクを備えた製品もありますが、フードの鮮度管理が必要になります。そのため、定期的な点検や掃除を行い、うさぎの健康に配慮することが重要です。
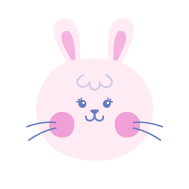
このように、自動給餌器は忙しい飼い主にとって非常に便利なアイテムですが、適切なモデルを選び、正しく運用することが大切です。自分のライフスタイルやうさぎの食習慣に合ったものを選ぶことで、健康的な食生活をサポートできるでしょう。
どのくらいの容量が必要?

自動給餌器を選ぶ際に重要なのが「容量」です。うさぎの食事量は体格や年齢、食習慣によって異なりますが、基本的に1日に必要なペレットの量は体重の約5%程度とされています。例えば、1kgのうさぎであれば1日あたり約50g、2kgのうさぎなら約100gのペレットが必要になります。
一般的な自動給餌器のタンク容量は、1.5L~4L程度の範囲で販売されており、それぞれの特徴が異なります。例えば、1.5L~2Lクラスの給餌器はコンパクトで場所を取らないため、日常的な給餌に便利です。ただし、容量が小さいため頻繁に補充する必要があり、長期間の留守には向いていません。一方、3L~4Lクラスの大容量タイプは、1週間分以上のペレットを貯蔵できるため、旅行や出張時の給餌にも適しています。
ただし、大容量だからといって必ずしも最適とは限りません。うさぎは新鮮なフードを好むため、長期間タンクに入れっぱなしにすると湿気や酸化で劣化するリスクがあります。そのため、数日に一度はタンク内のフードをチェックし、補充や交換を行うことが推奨されます。
また、給餌器の設計によっては、一度に排出できる量が制限されている場合もあります。特に、細かい量を調整できるモデルであれば、健康管理に役立つ一方で、大量のペレットを一気に給餌したい場合には向いていません。機種によって給餌設定の最小単位や最大給餌量が異なるため、選ぶ際には具体的なスペックを確認することが重要です。
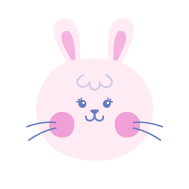
このように、給餌器の容量はライフスタイルやうさぎの食習慣によって適切なものを選ぶ必要があります。頻繁に補充できるならコンパクトなものを、長期間の留守が多いなら大容量タイプを選ぶとよいでしょう。うさぎの健康を第一に考えつつ、使いやすさとのバランスを考慮して選ぶことが大切です。
カメラ付きオートフィーダーの撮影範囲

カメラ付きのオートフィーダーは、遠隔でうさぎの様子を確認できるため、安心感を得られる便利な機能です。しかし、カメラの撮影範囲や画質は機種によって異なるため、選ぶ際にはスペックをしっかり確認することが重要です。
一般的に、カメラ付きオートフィーダーの視野角は110°~130°程度が標準的で、広角レンズを搭載しているモデルが多くなっています。例えば、水平方向に125°、垂直方向に75°の視野を持つ製品であれば、給餌エリアだけでなく、ある程度広範囲のケージ内の様子を映すことができます。ただし、広角すぎると映像の端が歪むことがあるため、適度な視野角の製品を選ぶことが大切です。
また、カメラの解像度も重要なポイントです。1080p(フルHD)の高画質モデルであれば、細かい表情や動きまでしっかり確認できます。一方で、解像度が低いモデルでは、映像が粗くなり、暗い場所ではさらに見づらくなることがあります。そのため、夜間でもうさぎの様子を確認できる赤外線暗視機能付きのカメラを搭載したモデルを選ぶと、昼夜を問わず安心して監視できます。
さらに、カメラの位置にも注目すべきです。オートフィーダーによってはカメラが本体の上部にあるものと、給餌口に近い位置にあるものがあり、映る範囲が異なります。例えば、カメラが高い位置にある場合、広範囲を見渡せますが、うさぎがフードを食べる姿は見えにくくなることがあります。逆に、低い位置にカメラがあると、うさぎの顔やフードの残量をしっかり確認できます。
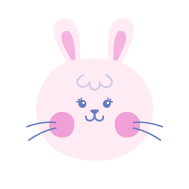
このように、カメラ付きオートフィーダーを選ぶ際は、視野角・解像度・夜間撮影機能・カメラの位置といった要素を総合的に考慮することが大切です。自分の使用環境に合ったスペックの製品を選ぶことで、より快適にうさぎの様子を確認できるでしょう。
停電時でも機能する?
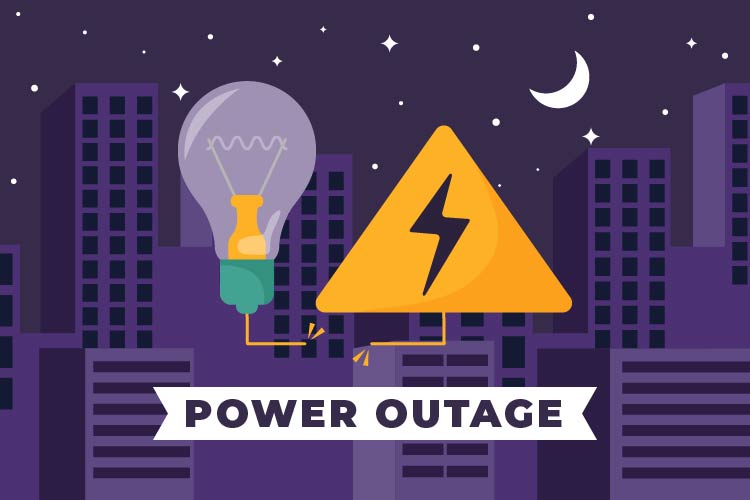
自動給餌器は、基本的に電力を利用して作動するため、停電時の動作については事前に確認しておく必要があります。特に長時間の留守中に停電が発生すると、給餌ができなくなる可能性があるため、対策を考えておくことが重要です。
現在、多くの自動給餌器は2WAY給電システムを採用しており、ACアダプター(コンセント)と乾電池の両方で動作できるようになっています。このシステムを搭載した機種であれば、普段はコンセントから電力を供給し、停電時には自動的に乾電池に切り替わるため、突然の停電が発生しても給餌機能が止まることはありません。
例えば、一部のモデルでは単3電池4本または単1電池4本を使用し、電池のみでも数週間から数か月間動作できる設計になっています。ただし、電池駆動時には給餌回数やその他の機能(カメラやアプリ連携)が制限される場合があるため、事前に確認が必要です。特に、Wi-Fi接続を利用するスマート給餌器では、停電時にルーターが使えなくなるため、遠隔操作ができなくなる可能性がある点にも注意が必要です。
また、停電対策として、以下のような工夫をすることで、より安心して使用できます。
- 定期的な電池の交換:乾電池の残量が少なくなると動作が不安定になるため、定期的に交換することが推奨されます。
- UPS(無停電電源装置)の利用:短時間の停電であれば、UPSを利用して電力供給を維持することで、電池を使わずに給餌器を動作させられる場合があります。
- 停電時の代替策の準備:長期間の停電が予想される場合は、手動での給餌やペットシッターの利用など、別の対策も考えておくと安心です。
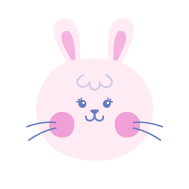
このように、停電時でも給餌ができるようにするには、2WAY給電の製品を選び、電池の管理をしっかり行うことが大切です。特に長期間の外出が多い場合は、事前に十分な対策をしておくことで、万が一の事態にも対応しやすくなります。
使えるペレットの種類と注意点

自動給餌器を使用する際には、ペレットの種類と給餌器の構造が適合しているかを確認することが重要です。ペレットの形状や大きさによっては、正常に排出されなかったり、詰まりが発生する場合があるため、購入前に対応しているペレットの特徴を確認しましょう。
一般的に、自動給餌器で使用できるペレットは、以下の特徴を持っています。
- 形状が均一:小粒で丸みのあるペレットが詰まりにくく、スムーズに給餌されやすいです。細長い形状のペレットや、ばらつきのあるサイズのペレットは、詰まりの原因となることがあります。
- 適度な硬さ:柔らかすぎるペレットは粉状になりやすく、給餌器内で詰まるリスクが高まります。しっかりとした固さのあるペレットが適しています。
- 直径の確認:多くの自動給餌器は、5mm~10mm程度のペレットに対応しています。大粒や特殊形状のものは、スムーズに排出されない可能性があります。
また、以下のようなフードは詰まりやすいため、使用を避けることが推奨されます。
- 湿ったペレット:水分を多く含むペレットや、ウェットフードは給餌器の内部に張り付きやすく、故障の原因になります。
- 粉末状のフード:細かい粉状のペレットは、給餌器の内部で溜まり、詰まりやすくなるため注意が必要です。
- ベタつきやすいフード:糖分や油分を含むペレットは、内部に付着しやすく、定期的な掃除が必要になります。
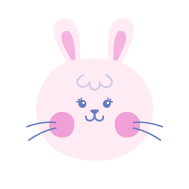
自動給餌器を長期間快適に使用するためには、ペレットの選び方と給餌器のメンテナンスが重要です。定期的に内部の掃除を行い、詰まりを防ぐことで、スムーズな給餌を維持できます。また、新しいペレットを使用する際には、少量ずつ試し、問題なく給餌されるかを確認すると安心です。
どのくらいのケージに取り付けられる?

自動給餌器を選ぶ際には、使用するケージに適合するかを事前に確認することが大切です。うさぎ用のケージは種類が多いため、給餌器の取り付け方法によっては、しっかり固定できない場合があります。
一般的に、自動給餌器の取り付け方法には以下の2種類があります。
- 据え置き型:ケージの外に設置し、トレー部分をケージ内に向けるタイプ。ケージに直接固定しないため、置き場所を自由に調整できるメリットがあります。ただし、ケージが狭い場合は設置スペースを考慮する必要があります。
- ケージ取り付け型:ケージのワイヤー部分に固定できるタイプで、省スペースで使用できるのが特徴です。ただし、ワイヤーの間隔や太さによっては取り付けが難しい場合があります。
一般的なケージに取り付けられる目安として、ワイヤーの間隔が21mm~44mm、ワイヤーの直径が5mm以下であれば、多くの給餌器が対応可能です。特に、マルカンなどのメーカーが販売しているケージ取り付け型のオートフィーダーは、ワイヤーケージ向けに設計されており、簡単に固定できます。
一方で、プラスチック製やアクリル製のケージを使用している場合、ワイヤー部分が少ないため、取り付けが難しくなることがあります。その場合は、据え置き型の給餌器を選ぶか、専用の固定パーツを利用することで対応可能です。
また、ケージの高さも重要なポイントです。自動給餌器の給餌口の位置が低すぎると、うさぎが食べにくくなるため、適切な高さに調整できるモデルを選ぶことが望ましいです。特に、成長段階にあるうさぎの場合、設置後に高さを変更できるタイプを選ぶと長く使えます。
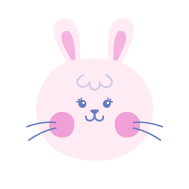
このように、自動給餌器を選ぶ際は、ケージの種類、ワイヤーの間隔、高さの調整などを総合的に考慮し、最適なものを選ぶことが重要です。購入前にケージのサイズや仕様を確認し、しっかり取り付けられるかをチェックすると、スムーズに設置できます。
ケージの種類による取り付け方の違い
自動給餌器を設置する際は、ケージの種類に応じた適切な取り付け方法を選ぶことが重要です。うさぎ用のケージには、ワイヤーケージ、プラスチックケージ、アクリルケージなど様々な種類があり、それぞれ設置方法が異なります。
まず、多くのうさぎ飼育者が使用しているワイヤーケージの場合、自動給餌器の取り付けは比較的簡単です。一般的な自動給餌器には、ケージのワイヤー部分に固定できるクリップやフックが付属しており、工具を使わずに設置できるモデルが多くなっています。ただし、ワイヤーの間隔が広すぎると固定が甘くなり、給餌時に不安定になる可能性があるため、取り付ける前にケージのワイヤー幅を確認しておくとよいでしょう。
一方で、プラスチック製やアクリル製のケージの場合、ワイヤーがないため、直接固定することが難しいケースがあります。この場合、据え置き型の給餌器を選ぶのが一般的です。給餌器の下部に滑り止めが付いているタイプを選ぶと、ケージ内でずれるのを防ぐことができます。また、吸盤や専用の固定パーツを使用して取り付ける方法もありますが、プラスチックやアクリルは滑りやすいため、しっかり固定できるか事前に確認しておく必要があります。
さらに、ケージの種類によっては、給餌器の高さ調整が必要になることもあります。例えば、小型のうさぎを飼育している場合、給餌口の位置が高すぎるとフードが取りづらくなります。逆に、大型のうさぎの場合、低すぎると食べにくくなり、給餌器を蹴ったり倒したりするリスクもあります。そのため、高さを調節できるモデルを選ぶか、台を使って高さを調整すると、より快適に使用できます。
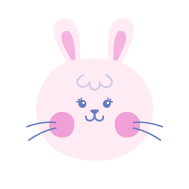
このように、ケージの素材や構造によって取り付け方は大きく異なります。ワイヤーケージなら固定型、プラスチック・アクリルケージなら据え置き型が適していることを理解し、最適な方法で設置することが重要です。事前にケージの仕様を確認し、うさぎが快適に食事できるように調整することをおすすめします。
👇餌についてもオススメを下記記事に紹介していますので見てみてください!👇
\👇うさぎの給水ボトルについても紹介していますので見てみてください!👇/
うさぎ 自動給餌器 オートフィーダー おすすめの製品と比較
- おすすめの自動給餌器3選
- 口コミや評判をもっと知りたい
- 自動給餌器の音がうさぎにストレスを与える?
- 音を減らす方法と具体的な設定
- 音を減らすためのアクセサリーとメーカーおすすめ製品
- 牧草対応のオートフィーダーはある?
- 牧草フィーダーの容量・価格・選び方
おすすめの自動給餌器3選
うさぎ用の自動給餌器にはさまざまな種類がありますが、ここでは機能性・使いやすさ・口コミ評価の観点からおすすめの3つを紹介します。
1. ミニマルランド うさぎの安心オートフィーダースマート カメラ付き

・お留守番中もスマホで様子が見られて安心。かわいい写真や動画を撮影できるうさぎ用カメラ付きオートフィーダーです。 ・呼びかけや会話ができるマイク&スピーカー付。 ・停電の際にも安心の2WAY給電式 【対応ケージ】ワイヤーの間隔:21~44mm、ワイヤー直径5mm以下のケージ
2.ミニマルランド うさぎの安心オートフィーダー

あらかじめケージフェンスのワイヤー径や間隔をお調べください。間隔21~44mm、ワイヤー径5mm以下、間隔44mm以上、ワイヤー径8mm以下の場合は使用可能です。うさぎのスッキリおそうじケージ、うさぎのカンタンおそうじケージシリーズへのご使用がオススメです。食器は本体から約45mmまで下げることが可能ですので、設置位置をご調整ください。ケージトレイ側面が高い、カバー付きのケージにご使用の場合は、ケージ床面から食器までの高さを考慮し、食事がしにくくなる場合はステップなどを別途ご用意ください。
3. 小動物 自動給餌器 エサ入れ 電源不要 重力式

【大容量】:1 Lの貯蔵容量で、一時的な外出でも、ペットが留守番をしている間に食糧不足の心配はありません。
【電気不要】:この自動給餌器は、重力の原理を採用して、ペットに新鮮な食べ物を継続的に供給するため、ペットが飲むすべての穀物が新鮮です。
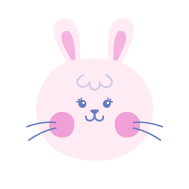
このように、自動給餌器にはさまざまな種類があり、容量・電源方式・追加機能によって選び方が変わります。自分のライフスタイルやうさぎの食習慣に合ったものを選ぶことで、より快適に使用できるでしょう。
口コミや評判をもっと知りたい
自動給餌器の購入を検討する際、実際に使用した飼い主の口コミや評判を参考にするのは非常に有益です。特に、使い勝手や耐久性、うさぎの反応など、実際の使用感を知ることで、自分に合った製品を選びやすくなります。
多くの口コミでは、「時間通りに餌をあげられるため、外出時でも安心」「毎朝の餌やりの手間が減って楽になった」といった利便性の高さが評価されています。特に、仕事が忙しく決まった時間に給餌できない方にとって、自動給餌器は非常に役立つアイテムのようです。

「時間通りに餌をあげられるため、外出時でも安心」

「毎朝の餌やりの手間が減って楽になった」
一方で、「ケージへの取り付けが難しかった」「ペレットが詰まることがある」といった設置や動作に関する問題を指摘する声もあります。特に、細長いペレットや粉っぽいペレットは詰まりやすいため、適切なフードを選ぶことが重要です。また、ワイヤーケージ以外のケージでは取り付けが難しく、工夫が必要な場合もあるため、設置方法を確認してから購入することをおすすめします。

「ケージへの取り付けが難しかった」
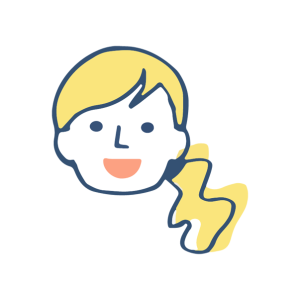
「ペレットが詰まることがある」
また、音に関する口コミも多く見られます。「給餌の際の音が思ったより大きく、最初はうさぎが驚いていた」という意見もありますが、「数日で慣れて問題なく食べるようになった」との声も多く、慣れさせることがポイントになりそうです。
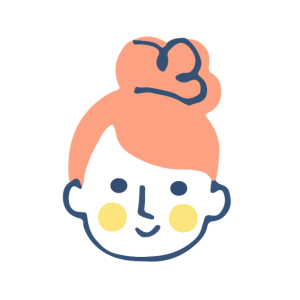
「給餌の際の音が思ったより大きく、最初はうさぎが驚いていた」

「数日で慣れて問題なく食べるようになった」
このように、口コミを参考にすることで、実際の使用感や注意点を把握できます。購入前にレビューをチェックし、設置方法や対応するペレットの種類を確認することが重要です。自分のうさぎに合ったモデルを選ぶことで、より快適に使用できるでしょう。
自動給餌器の音がうさぎにストレスを与える?

うさぎは聴覚が非常に発達しており、突然の大きな音や機械音に敏感に反応する動物です。そのため、自動給餌器の動作音がストレスの原因になる可能性があります。特に、初めて自動給餌器を導入する場合、うさぎが慣れるまでの間は注意が必要です。
一般的な自動給餌器は、ペレットを排出する際にモーターが動作し、カラカラとした音が発生します。また、ペレットがトレイに落ちる際に、受け皿の材質によっては大きな音が鳴ることもあります。この音に驚いたり、不安を感じたりするうさぎもいるため、事前に対策を考えておくことが大切です。
特に、臆病な性格のうさぎや、環境の変化に敏感な個体では、音に驚いて給餌器を避けるようになったり、ストレスによって食欲が低下するケースも報告されています。うさぎがストレスを感じているサインとして、以下のような行動が見られることがあります。
- 給餌器の近くに行こうとしない
- 給餌の時間になると隠れる
- 以前より食欲が落ちた
- 急にケージの隅でじっとするようになった
ただし、すべてのうさぎが自動給餌器の音を怖がるわけではありません。**最初は警戒していても、時間が経つにつれて慣れ、問題なく使用できるようになることが多いです。**音に対する慣れの程度は個体差があるため、導入時には様子を観察しながら慎重に進めることが大切です。
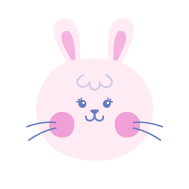
このように、自動給餌器の音はうさぎにストレスを与える可能性がありますが、適切な対策を取ることで、安心して使用できるようになるでしょう。
音を減らす方法と具体的な設定
自動給餌器の音が気になる場合は、設置方法や設定を工夫することで、音を軽減することが可能です。うさぎが音に驚かないようにするために、以下のような方法を試してみるとよいでしょう。
1. 設置場所の工夫
- ケージの壁から少し離して設置する:壁に近すぎると音が反響し、大きく聞こえてしまうため、少し間隔を空けるとよいです。
- 防音マットや布の上に置く:給餌器の振動が床や棚に伝わることで、余計な音が発生することがあります。柔らかいマットや布を敷くことで、振動音を軽減できます。
2. 給餌量と回数の調整
- 一度に出るペレットの量を少なくする:大量のペレットを一気に排出すると、受け皿に当たる音が大きくなります。給餌量を少なくし、回数を増やすことで、音を小さくすることができます。
- 静かな時間帯に給餌する:夜間や早朝は環境音が少ないため、自動給餌器の音がより響きやすくなります。うさぎが比較的リラックスしている時間帯に設定することで、ストレスを軽減できます。
3. 受け皿の材質を変更する
- ステンレス製の受け皿からプラスチックやシリコン製のものに変える:金属製の受け皿はペレットが当たる音が響きやすいため、静音性の高い材質の受け皿に交換するのがおすすめです。
- 受け皿の下にクッションを敷く:衝撃を和らげることで、音を減らすことができます。
4. 慣れさせる工夫
- 最初は手動で給餌してみる:音に慣れるまで、手動で少しずつペレットを出し、うさぎが安心して食べられる環境を作るとよいです。
- 給餌時に声をかける:「ごはんだよ」といった声掛けを行うことで、給餌器の作動音と飼い主の声を関連付け、安心感を与えることができます。
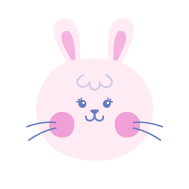
このように、給餌器の設置方法や設定を工夫することで、音を抑えつつ、うさぎが安心して食べられる環境を作ることが可能です。
音を減らすためのアクセサリー
自動給餌器の音を減らすためには、専用のアクセサリーや静音性に優れた製品を選ぶことも有効な対策になります。特に、静かに動作するモデルを選ぶことで、うさぎのストレスを最小限に抑えることができます。
音を軽減するアクセサリー
- 防音マット:給餌器の下に敷くことで、振動音を吸収し、床や棚への響きを抑えることができます。
- シリコン製の受け皿:ペレットが当たる音を軽減し、うさぎが驚きにくくなります。
- 防音パネル:ケージの周囲に設置することで、音の反響を抑えることができます。
- 静音モーター用の潤滑剤:摩擦音を抑え、給餌時の音を小さくする効果が期待できます。
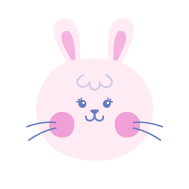
このように、音を軽減できるアクセサリーを活用することで、うさぎのストレスを抑えながら快適に給餌することが可能です。購入前に製品のレビューを確認し、うさぎの生活環境に合ったものを選ぶことが大切です。
牧草対応のオートフィーダーはある?
うさぎの主食である牧草に対応した自動給餌器(オートフィーダー)は、現時点ではあまり一般的ではありません。ペレット用の自動給餌器は多く販売されていますが、牧草は軽くて形状が不均一なため、自動で適切に供給することが難しく、市販の製品の多くはペレット専用として設計されています。
しかし、一部のメーカーからは牧草を給餌しやすい設計のフィーダーが販売されており、飼い主が少ない手間で牧草を管理できる製品もあります。これらは厳密には「自動給餌器」ではありませんが、適切な量の牧草をいつでも食べられる状態にするという点では、給餌管理をサポートする重要なアイテムと言えます。
おすすめ牧草フィーダー

マルカン 牧草用エコフィーダー ワイド 小動物用 食器 給水器 ロング牧草も入れやすい

NEXT.C.C チモシー入れ 3点固定 大容量 うさぎ 牧草入れ ワイド 木製 牧草 フィーダー チモシー 餌入れ チンチラ デグー モルモット

Asdays 牧草ポット ウサギ チモシー 餌入れ フィーダー 小動物 モルモット 食器 餌箱 こぼれにくい 固定可能 ホワイト
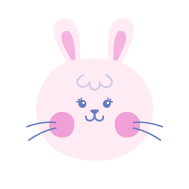
このように、牧草を供給しやすい製品はいくつか販売されていますが、完全自動で給餌するオートフィーダーはまだ一般的ではありません。ただし、牧草は常に新鮮なものを補充する必要があるため、適度に管理できるフィーダーを活用しながら、手動での補充を併用するのが現実的な運用方法といえます。
牧草フィーダーの容量・価格・選び方
牧草フィーダーを選ぶ際には、容量・価格・設置方法などの要素を考慮することが重要です。うさぎがいつでも新鮮な牧草を食べられるようにするためには、適切なサイズと機能を備えたフィーダーを選ぶことが大切です。
牧草フィーダーの容量
フィーダーの容量は、うさぎの食事量や留守にする時間に応じて適切なものを選ぶ必要があります。一般的には、以下のような容量の製品が販売されています。
- 小容量タイプ(0.5L~1L)
- 1日分程度の牧草を入れられる
- 毎日新しい牧草を補充したい場合に適している
- うさぎが牧草を食べすぎるのを防ぐ効果もある
- 中容量タイプ(1.5L~2.5L)
- 1~2日分の牧草をストック可能
- 仕事などで日中不在が多い家庭に向いている
- 固定型・据え置き型ともに選択肢が豊富
- 大容量タイプ(3L以上)
- 3~4日分の牧草を補充できる
- 長時間の外出や旅行時に便利だが、牧草の鮮度管理が必要
- 牧草の湿気対策が求められるため、通気性の良い設計が理想的
牧草フィーダーの価格帯
牧草フィーダーの価格は、材質・容量・機能によって異なります。一般的な価格帯は以下のようになります。
- 低価格帯(1,000円~2,000円)
- プラスチック製やワイヤー製のシンプルなフィーダー
- 小型で、毎日補充するスタイルの飼い主向け
- 中価格帯(2,000円~3,500円)
- 牧草の飛び散りを防ぐ設計がされた製品が多い
- ワイヤーケージ取り付け型やストッカー式が主流
- 高価格帯(3,500円以上)
- セラミック製やステンレス製の耐久性が高いモデル
- 牧草の鮮度を保つ機能や、大容量設計のものが多い
牧草フィーダーの選び方
牧草フィーダーを選ぶ際には、以下のポイントを考慮することで、より使いやすい製品を選ぶことができます。
- 設置方法
- ワイヤーケージ向け:クリップやフックで簡単に取り付け可能
- 据え置き型:ケージの床に置いて使用するため、大容量の牧草を入れられる
- 掃除のしやすさ
- 取り外しが簡単なフィーダーは、定期的な清掃がしやすく、清潔な環境を保てる
- 牧草の取り出しやすさ
- うさぎがストレスなく牧草を食べられるよう、適度な隙間がある設計が理想的
- 散らかり防止機能
- 牧草の飛び散りを抑えるストッパーやカバー付きのものを選ぶと、掃除の手間が軽減できる
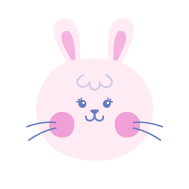
このように、牧草フィーダーの容量や機能は、うさぎの食事スタイルや飼い主のライフスタイルに合わせて選ぶことが重要です。適切な製品を選ぶことで、うさぎがいつでも新鮮な牧草を食べられる環境を整え、健康を維持することができます。
まとめ:うさぎ 自動給餌器 オートフィーダー おすすめの選び方とポイント
- 自動給餌器は設定時間にペレットを自動供給できる便利な機器
- 1日2~4回の給餌設定が可能で、ペレットの量も調整できる
- カメラ付きモデルなら遠隔でうさぎの様子を確認できる
- 容量は1.5L~4Lが一般的で、飼い主の生活スタイルに合わせて選ぶ
- ペレットの鮮度を保つため、大容量タイプでも定期的な補充が必要
- 停電対策には2WAY給電(ACアダプター+乾電池)対応モデルが安心
- 細長いペレットや湿ったフードは詰まりやすいため使用に注意
- ワイヤーケージなら取り付け型、プラスチックケージなら据え置き型が適している
- 給餌器の音がうさぎにストレスを与える場合は、防音マットなどの対策が有効
- 音を抑えるには給餌量を減らし回数を増やすのも効果的
- 静音設計の製品やシリコン製の受け皿を選ぶと音が気になりにくい
- 牧草専用の自動給餌器は少なく、牧草フィーダーを併用するのが現実的
- 牧草フィーダーは小容量(1L)、中容量(2L)、大容量(3L以上)から選べる
- 価格帯は1,000円~4,000円程度で、素材や機能によって異なる
- 口コミでは「便利だが、音やペレット詰まりに注意」との声が多い
関連記事
-

-
うさぎケージ 2段重ねは安全?失敗しない選び方と注意点
2025/7/15
うさぎを多頭飼いしている、あるいはこれから飼いたいと考えている方にとって、「うさぎ ケージ 2段 重ね」というスタイルは省スペースで便利に思えるかもしれません。とはいえ、実際に導入するとなると安全性や ...
-

-
うさぎ 給水 ボトルは良くない?後悔しない選び方と工夫を解説
2025/7/14
うさぎを飼っている方の中には、「うさぎ 給水 ボトル 良く ない」といったキーワードで情報を探している方も多いのではないでしょうか。うさぎの給水ボトルは「良くない」と言われる理由として、飲みにくさや水 ...
-
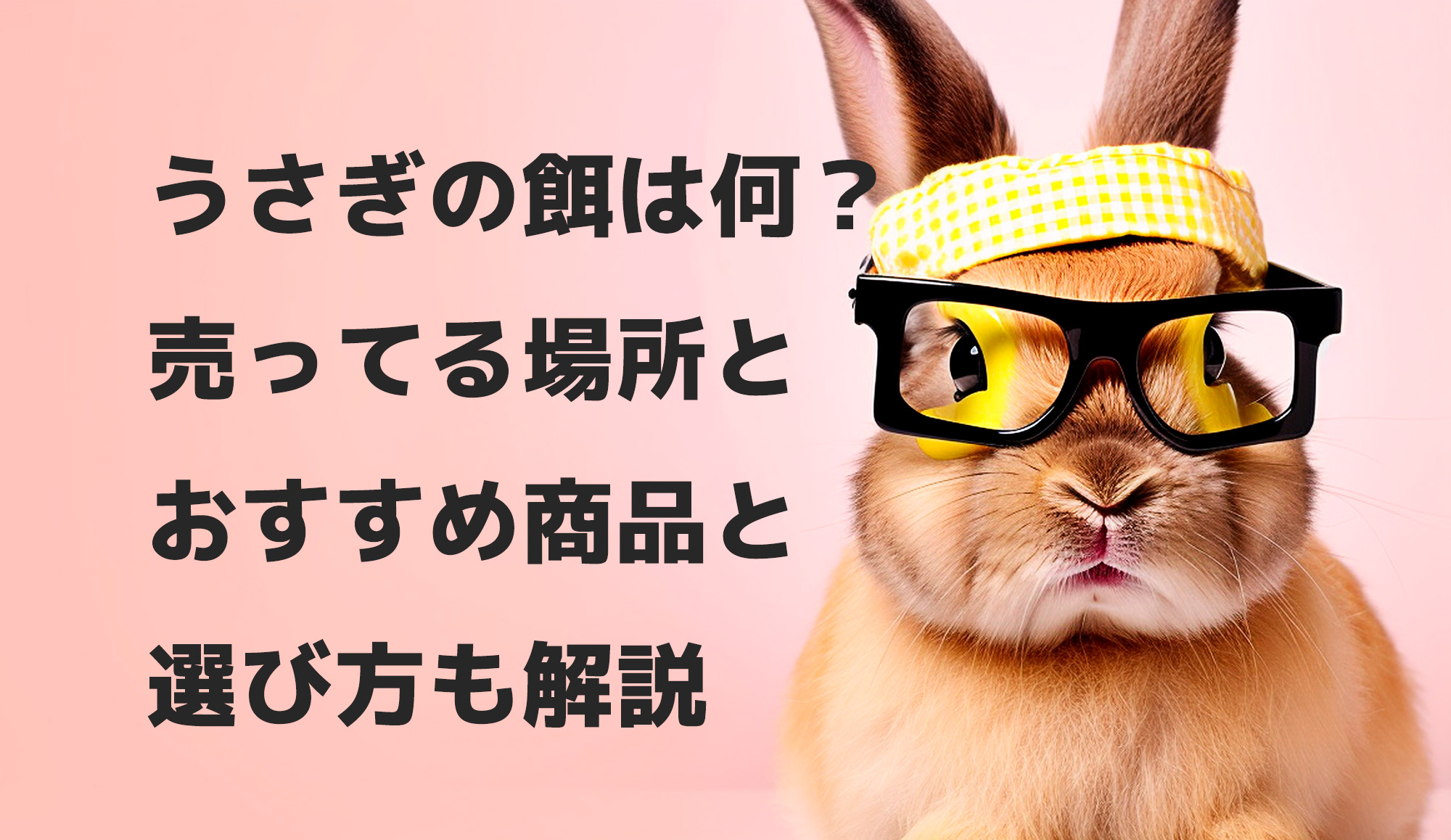
-
うさぎの餌は何? 売ってる場所とおすすめ商品と選び方も解説
2025/7/15
うさぎを飼い始めると、まず気になるのが「うさぎの餌の売ってる場所」ではないでしょうか。どこで餌を購入できるのかだけでなく、餌はなに?ペレットって?チモシーって?といった基本的な知識も押さえておくことが ...
-

-
【2025年版】うさぎ用自動給餌器(オートフィーダー) おすすめと選び方を詳しく説明します。
2025/7/15
この記事はプロモーションを含みます うさぎの健康を維持するためには、適切な時間と量での給餌が欠かせません。しかし、仕事や外出が多いと、毎回決まった時間に餌を与えるのが難しくなることもあります。そんなと ...